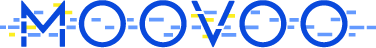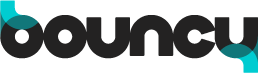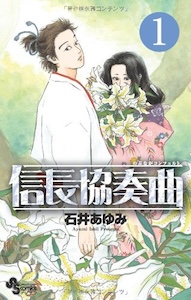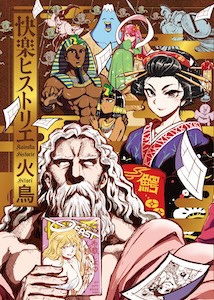歴史漫画おすすめ名作20選 小・中学生から歴史を楽しく知れる
歴史漫画は、過去から今につながるとてもドラマチックなエピソードを凝縮している漫画です。大人が楽しむだけでなく、小学生や中学生にとって歴史学習への意欲にもつながるため、さまざまな名作が長く人気を維持しています。
長い歴史の中で起きた壮大なストーリーは、歴史を好きでない人の心もつかみます。
この記事では、名作として愛されるおすすめの歴史漫画を紹介します。ぜひ楽しんでみてください。
- 楽天
-
楽天kobo電子書籍ストア
-
400万冊の中から、好きな作品を選んでスマホで楽しめる
-
スマホやパソコンなどで好きなマンガを好きなときに楽しめる総合電子書籍ストア。
品揃えは400万冊、多彩なジャンルから選べます。楽天ポイントが貯まり、貯めたポイントで新たな作品が読めるのも魅力です。
歴史漫画は楽しみながら知識を吸収できる
漫画と書籍(活字)の大きな違いは、イラストの有無だと言えるでしょう。いわゆる参考書や図鑑にも図版はありますが、明らかに情報の主体はテキストです。
しかし歴史漫画の場合は、イラストが主体です。1コマの中にも当時の衣装や風俗を反映しています。しかも、文字だったら一行で済む記述も全て描く必要があるので、歴史物語の臨場感が高まります。
当時の人たちはどんな服を着ていたのか、何を食べていたのかなど興味は尽きません。この臨場感の高まりが歴史漫画の面白さなのです。
歴史漫画の名作からおすすめ20選を紹介
一作目は阿吽、日本の仏教や文化の礎となった平安仏教の巨人、空海(弘法大師)と最澄(伝教大師)のダブル主人公ものです。
平安時代といえば源氏物語などの文化面ばかりが強調されますが、仏教という視点は非常に新しいものです。おそらく多くの歴史ファンにとっても盲点になっていたと言えるでしょう。
仏道を追求する二人の生きざまは凄まじく、史実をなぞりながらもエキサイティング。平安時代という中世を多角的に見れる歴史漫画の傑作です。
歴史漫画と言えば定番とも言えるのが、みなもと太郎先生の風雲児たち。幕末を舞台した群雄伝の傑作です。絵柄やコマ割りが昭和チックで古風なので、第一印象で切り捨ててしまう人がいるかもしれませんが、それはあまりにも早計だと言えます。
少しでも読み始めれば、次々とページをめくる手が止まらなくなるでしょう。幕末のイメージが相当変わるので、特に司馬遼太郎ファンの人には是非読んで欲しい歴史漫画です。
風光るは、性別を偽って新選組に入隊した少女を主人公にした幕末の歴史漫画です。女流作者の作品ということもあり、江戸と京都の屋根の形の違いやお歯黒や髪型といった時代背景や身の回りの描写が非常に細かく、勉強になります。歴史考証がしっかりした少女漫画としての幕末漫画だと言っても良いかと思います。
みなもと太郎先生の風雲児たちと同時並行で読むと、幕末について多角的な理解が得られるでしょう。
ヒストリエはアレキサンダー大王(イスカンダル大王)の書記、エウメデスを主人公にした作品です。
いわゆる歴史漫画の多くはキャラクターのマインドが現代人寄りにならざるを得ません。当時の価値観をリアルに導入すると現代人的感覚とバッティングするので共感できないからです。しかし本作ではそのような心配は無用です。
作中に漂う人権意識や倫理など微塵もない殺伐として残酷な雰囲気は、まさに紀元前の物語だと言えるでしょう。
なかなか新刊が出ないのが玉に瑕ですが、未読の人にとってはまとめ読みできる楽しみが残っています。是非手に取って欲しい名作です。
アンゴルモアはサブタイトル通り元寇(文永の役)を題材にした歴史漫画です。
元寇というと当時世界最強の元(モンゴル)の侵略に対して、名乗りを上げて一騎打ちを挑んだ鎌倉武士が惨敗し、台風という幸運でからくも撃退できたというのが歴史の通説でした。これは昭和時代の歴史教科書や学習漫画でも同様の記述があります。
しかし近年は、研究により鎌倉幕府が元寇を退ける事が出来た理由について歴史の真実が明らかになりつつあります。
アンゴルモアでは泥臭く抵抗を繰り返す鎌倉武士の戦いを描いています。若干のフィクション要素を含めて漫画としてのクオリティは高く、アニメ化もされているくらいです。
「元寇=ちょうど台風が来るという幸運で勝てた」と思っている人は是非読んでみてください。きっと驚くでしょう。
「へうげもの」という珍しいタイトルは「ひょうげもの」と発音し、ふざける、おどける者という意味があります。これは主人公の戦国武将、古田織部を指します。
彼は戦国時代の終わりから安土桃山時代を織田信長と豊臣秀吉に仕えました。戦国武将として動乱の時代を生き抜いてきたシビアさを持ちながら芸術を追及する一面もあり、「数寄者」としても有名です。
その最後は史実通りなのですが、政治家や戦闘者としてのイメージが強い戦国武将の人間的な側面が生々しく描かれており本当に素晴らしい作品です。
最終巻のラストはまさに泣き笑いとしか言いようのない感動に包まれます。
へうげものとほぼ同時期を舞台にしており、こちらは前田慶次を主人公としています。戦国武将の芸術面を強調したへうげものとはやや違い、こちらは傾奇者としての一面を描いており、命がいつまであるかわからない戦士の心意気が感じられます。
やや強めのアレンジが効いているのでバトル漫画的表現がありますが、注目すべきは豊臣秀吉の合扱いです。
織田信長を主人公にした作品では「サル」などと呼ばれ、調子のいい小兵に過ぎない秀吉が天下人として描かれており圧倒的な支配者のカリスマに満ち溢れています。
同一人物の描写がこうまで変わってしまうのが歴史漫画の面白いところです。多面的に人物を評価する練習になるでしょう。
本作は「のぶながきょうそうきょく」ではなく「のぶながコンツェルト」と読みます。協奏曲というタイトルどおりキャラクターの人間関係に重点が置かれています。
そもそも戦国武将の中でも織田信長ほど多く語られた人物はいないでしょう。そのイメージは様々ですが、概ね先進的な暴君としての一面が強調される事が多いかと思います。しかし、信長協奏曲の信長はタイムスリップした高校生に過ぎません。何となく脱力した青年信長像とそれを取り巻く家臣たちは新しい切り口だといえます。
是非他の戦国時代を題材にした漫画と読み比べてみてください。作者によって同じ人物がこうも異なるイメージで描かれる事にびっくりするでしょう。
天地明察は江戸時代を舞台に大和歴を作った天文学者、渋川春海の生涯を描いた作品です。原作は幾多の賞を獲得した小説ですが、映画化と合わせてコミカライズされており非常にハイクオリティに仕上がっています。
渋川春海が作った大和歴とは当時の日本独自の暦(こよみ)の事です。カレンダー作りというと大したことのない仕事のように思えるかもしれませんが、暦を作り管理することは支配者として時間を支配するのと同義なのです。
暦がズレ始めると農業の作付け日がズレて収穫にも影響を及ぼすことを思えば、まさに国家の一大事業だといえます。
江戸時代の算術(数学)、天文学、暦の権威者である朝廷など全く新しい切り口が次々と語られるのは非常に新鮮です。時代劇ファンこそぜひ読んで欲しい歴史漫画の傑作です。
こちらも江戸時代の後期、1862年を舞台にしていますが、ある意味では現在大流行している「異世界転生」や「なろう系」作品の一種だといっても良いかもしれません。
作品の成立はJINの方が明らかに先ですが、脳外科医が江戸時代にタイムスリップして、様々な問題に直面しながら現在の医療技術(チート能力!)を活用して歴史上の偉人とかかわりを持つからです。嫉妬による妨害など様々な苦難を乗り越えていく南方仁を見ていると元気づけられます。
ドラマ化されるなど高い人気を誇る本作は、江戸の文化文物が住人の目線で細かく描写されており、非常に良質な歴史漫画でもあります。読みだしたら止まらないくらい面白いので是非チェックしてみてください。
ローマ人の風呂技術者が現代日本にタイムスリップしてカルチャーギャップや知的刺激を受ける、というコメディが大ヒットした本作はイタリア人の夫を持つヤマザキ・マリ先生によるものです。
古代人が現代にびっくりする、という展開はさほど珍しいものではありませんが、本作は圧倒的にローマ文化の造詣が深いのが特徴です。作中で描かれるローマ人の服装や調度品、日常生活は全て歴史的考証に耐えるくらいのリアリティで描かれているのです。
本作を単なるギャグ漫画として読むのはあまりにももったいないと言えるでしょう。
ローマについて学びたいけど敷居が高いと感じる人は、まずは本作から手を付けてみてはいかがでしょうか。きっと興味がわいてくるはずです。
本作はテルマエ・ロマエの著者ヤマザキ・マリ先生が、ローマ帝国の博物学者として有名なプリニウスを主人公に据えた物語です。
テルマエ・ロマエは古代ローマと現代日本のカルチャーギャップを題材にしたコメディが中心でしたが、こちらはローマ成分100%。ローマ的なマインドが十全に描かれた歴史漫画です。
プリニウスの博物誌の中には、自分で確認していない伝聞による噂や迷信に過ぎない内容も紛れているので、現代人の感覚からすると百科事典のように全面的に信用できる書物ではありません。
しかし完成から1000年以上後のヨーロッパの知識人が愛読していたくらい、歴史的インパクトのある書物です。当時の人たちにとっての世界は胡乱なものだったのでしょう。
やはり厳密な歴史考証に基づく絵作りがリアリティを生み出しているといえます。テルマエ・ロマエでローマに興味を持った方なら楽しめる作品です。
乙嫁とは現代語で「弟の嫁」を意味しますが、テーマタイトルの意味する乙嫁とは若い嫁、可愛い嫁を意味する古語から付けられています。
乙嫁語りは、19世紀末、中央アジアのカスピ海周辺を舞台に様々な遊牧民族の夫婦や恋愛を描いた作品です。これまでほとんど注目されなかった戦争の時代が始まる前の遊牧民族の描写は全てが新鮮です。
彼らの暮らしぶりの描写が漫画化されたのは世界初だと思われますし、森薫先生によるあまりにも美麗なイラストにはため息が出るほどです。1コマたりとも雑な描写がありません。
作中ではロシア帝国が南下してくるという噂が流れており、最終的には国家という近代の枠組みを持たない彼らは取り込まれか、消滅するかすると思われます。
まさに最後の輝かしい瞬間を切りとっているのです。世界史で語られる事のない一つの物語がここにあります。是非チェックしてみてください。
13世紀末から14世紀のスイスを舞台ににした歴史漫画。ハプスブルグ家の圧政と戦う森林同盟三邦の物語ですが、中心となるのは交易路の要衝に建てられた狼の口と呼ばれる砦です。
この砦の城主は、極悪非道のヴォルフラム。彼の圧政を数巻にわたってじっくり描いてから、最後に杭打ちの刑で処刑するのが最大のカタルシスです。是非読んでください。ヴォルフラムが最後を迎えるまで、絶対に読むのをやめられなくなるでしょう。
中世の攻城戦が生々しく描かれており、スイス傭兵の精強さの理由が良く分かります。今でもバチカン市国の警備をしているのが納得ですね。
日本史・世界史のトリビアをエロ漫画に絡めて紹介する良質な大人のコメディが快楽ヒストリエです。快楽天ビーストというアダルト漫画雑誌に連載されていましたが、本作には18禁要素は一切ありません。
むしろかなりハイコンテクストな歴史トリビアを扱っており、歴史ネタに造詣が深い人ほど楽しめる歴史漫画と言えるでしょう。本作の面白さがじわじわ染みてくると、自発的に歴史本を読むようになるでしょう。
本作は「うしおととら」など、数々の名作少年漫画を書いてきた藤田和日郎先生の作品で、銃弾同士が衝突して一塊になったかちあい弾を巡るミステリーを導入にクリミアの天使と呼ばれた看護婦ナイチンゲールと彼女にとりついた幽霊の物語が始まります。
歴史漫画ではなく偉人漫画では?と思われるかもしれませんが、クリミア戦争と彼女の行った病院改革は歴史的異業です。
世界大戦と近代戦争の間の戦争というのは以外と盲点になっているかと思います。当時の戦争がどんな様子だったのか、どんな劣悪な状態で戦っていたのかなど世界史を知る上で臨場感が増す漫画だと言えるでしょう。
上下巻で完結しているので、是非手に取ってみてください。
ノーベル文学賞作家スヴェトラーナ アレクシエーヴィチによる同名のルポタージュをコミカライズしたものが、こちら。
これまで語る事がタブー(禁忌)とされていた、独ソにおけるロシア人女性兵士を題材としており、その過酷さには震えが来るほどです。
歴史の1コマにするにはまだ生々しすぎる告白は、読者に心に衝撃を与えるでしょう。原作と合わせてチェックしたい歴史漫画です!
山賊や追剥を意味するバンデット(Bandit)というタイトルで、鎌倉武士の価値観を描いた歴史漫画です。武士の荒々しさ、蛮性をこれでもか!と描写しており、NHK大河ドラマでは決して語られないような目を覆わんばかりの暴虐の嵐が吹き荒れます。
元寇を描いたアンゴルモアと合わせて読むと、中世の武人階級について教科書的な理解を超えて生々しいリアル感が得られるでしょう。
SNSでも話題になっており、「まさになめられたら殺す!」がキーワードです。
こちらは学習漫画としての世界史セットです。しかし単なるセットではなく、年表や暗記ブック、世界遺産辞典や人物学習辞典といった副読本が充実しています。成績アップという事で受験を射程に入れているのでしょう。
子どもの学習用に特化したシリーズだと言えるでしょう。
ただし学習用として使えるのは中学受験程度だと思われます。高校受験や大学受験のテキストとして学習用の歴史漫画として使うのは厳しいでしょう。
世界史トランプもついているので、遊びながら主要な人物を覚えられるので小さい子どもへのプレゼントとしてもおすすめです。
大手出版社がリリースする、日本史を学べる歴史漫画として、最も目を引くのが集英社のものです。既に150万部を突破しており、人気漫画家の手による表紙はまさにコレクションとしてふさわしいものだといえます。
またこういった学習漫画は低学年からでも読めますし、歴史初心者の入門用としては最適かと思います。
ボックスごと購入して、子どもへのプレゼントにすると喜ばれるでしょう。
こちらの記事もどうぞ
関連記事はこちら
マンガの記事はこちら
-
LINEの友達登録をお願いします!
LINE限定で、毎週の人気記事を配信します!

XでMoovooをフォロー!
Follow @moovoo_